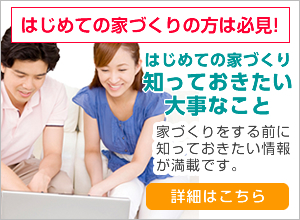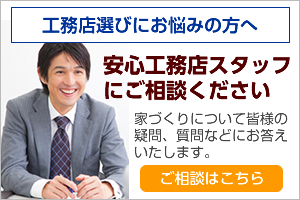はじめての家づくり
-知っておきたい大事なこと-
▼目次
住宅に関わる法律①/隣地とのトラブルを避けるために(民法234条・235条)
住宅の新築をする際、お隣の敷地との関係でトラブルになるケースがあります。民法では、隣地との境界線に関していくつか規定がされていますので、どのような法律なのかここで確認しておきましょう。
<民法234条(境界線付近の建築の制限)>
建築物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
このように民法では、建物を建てる際には境界線から50センチ以上離さなければならないと定められています。
これに違反して建築しようとすれば、お隣から建築中止や変更を求められることがあります。しかしすでに建物が完成してしまっている場合などには、損害賠償のみを請求できるとされています。
きれいに造成された住宅地などでは、ほとんどの家がこの規定を守り、境界線から余裕をもって建てられています。したがって、この問題に関するトラブルが発生する可能性は低そうです。
しかし、街の中をよく見てみますと、実際にはこの民法234条が守られていない住宅がかなり多いことに気づきます。限られた敷地に建物を建てる時に、なるべく敷地を有効に使いたいですし、少しでも広い家を建てたいと考えるのも当然といえば当然です。
民法で規定されていても、実際には守られないケースが多いのですが、これは一体どういうことなのでしょうか?
その答えをお伝えする前に、隣地との関係において同じような条文がありますので、まずはそちらを確認しておきましょう。
<民法235条(観望制限)>
境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2.前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地から近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
ここで書かれている目隠しとは、隣の人に家の中をのぞかれないように、いわゆるプライバシーを守るためのものです。たしかに、室内を他人に見られるのは嫌ですし、法律の趣旨はよくわかります。
しかし、境界線から1メートル未満の距離となれば、かなり該当する建物が出てきそうです。しかし、実際には目隠しを設置していないケースが多く、必ずしも遵守されてはいません。
先ほどの234条と同じように、民法に規定されながら現実には野放しになっているように見えますが、実は次の236条に以下のような規定があります。
<236条(境界線付近の建築に関する慣習)>
前2条の規定と異なる慣習がある時は、その慣習に従う。
つまり、地域の慣習として存在しているのならば、それが優先されるわけです。
古くからある町では住民同士の結びつきが強く、50センチだ目隠しだなどと他人行儀なことを言い合うような関係では、その町で暮らしていくことは難しいでしょう。また、日本人には「お互いさま」という文化もあり、すでに自分が民法の規定に抵触するような家に住んでいる場合などは、新しく来たお隣に対して文句を言うようなことも少ないと思います。都心部で建物が密集している地域などで、周辺ではほとんどの家が隣地から50センチ以内に建てているような場合など、すでに皆が了解済みであると見ることができます。
しかし、民法に規定がある以上、50センチの問題にしても目隠しの問題にしても、お隣から指摘されれば従わなければなりません。また目隠しの問題については、どちらか一方から見通せるということは、お隣からも同じように見通せるのだから、どっちが設置するべきなのかという疑問が残ります。これについては、基本的には後から建築する側が目隠しを設置しなければなりません(判例による)。
現実には、新築を計画する段階で隣地とのプライバシーを考慮して、窓の位置を考えるということが多いと思われます。大事なのは、こういった隣地が関係する時にはその後のお付き合いも考慮する必要があるということです。民法や慣習だけを持ち出して一方的に相手に要求をすることはトラブルのもとになります。ほとんどの人は民法に詳しいわけではありません。規定に抵触する建物を計画しているのであれば、ご自身の計画についてお隣にしっかりと説明し、合意を得ておくことがよいでしょう。
これらの法律は「しなければならない」という強制法規ではなく、「もし建物を境界近くに建てるなら、こういうルールをベースにしましょう」といった話し合いのベースを定めたものです。最後は当事者同士の話し合いで決まります。「民法に違反しているから、お隣は違法行為をしている」と騒ぎ立てるのではなく、お互いが納得できる着地点を見出すことが大事になります。

そして、ここまで述べてきたことはあくまでも民法に関する規定であり、境界線と建物の距離に関する決まりごとは、建築基準法(用途地域による制限)や地区計画条例、風致地区条例などが存在します。これらは民法とは違い、守らなければ建物が建てられない(建築確認申請が下りない)、あるいは罰則が科せられるなど、一定のペナルティがあり、実質上遵守しなければならないものがほとんどです。
隣地からどれくらい離さなければならないかは、建築する場所によって変わってきますので、用途地域や地区の条例などをよく調べた上で、計画を進めていきましょう。
▼目次